- シーンから探す
-
贈る相手から探す
- 彼氏
- 彼女
- 男友達
- 女友達
- 夫・旦那
- 妻・奥さん
- お父さん・父
- お母さん・母
- 両親
- おじいちゃん・祖父
- おばあちゃん・祖母
- 女性
- 男性・メンズ
- 妊婦
- 同僚
- 同僚(男)
- 同僚(女)
- 上司(男)
- 上司(女)
- 部下
- ビジネスパートナー・取引先
- 夫婦
- カップル
- 親友
- 女の子
- 子供
- 男の子
- 赤ちゃん・ベビー
- 乳幼児
- 1歳の誕生日プレゼント
- 2歳の誕生日プレゼント
- 3歳の誕生日プレゼント
- 4歳の誕生日プレゼント
- 5歳の誕生日プレゼント
- 6歳の誕生日プレゼント
- 7歳の誕生日プレゼント
- 8歳の誕生日プレゼント
- 9歳の誕生日プレゼント
- 10歳の誕生日プレゼント
- 18歳の誕生日プレゼント
- 19歳の誕生日プレゼント
- 20歳の誕生日プレゼント
- 21歳の誕生日プレゼント
- 22歳の誕生日プレゼント
- 25歳の誕生日プレゼント
- 26歳の誕生日プレゼント
- 30歳の誕生日プレゼント
- 40歳の誕生日プレゼント
- 50歳の誕生日プレゼント
- 60歳の誕生日プレゼント
- 70歳の誕生日プレゼント
- 80歳の誕生日プレゼント
- 88歳の誕生日プレゼント
- 90歳の誕生日プレゼント
-
カテゴリから探す
- 名入れギフト
- 記念品
- 文房具
- 花
- ビューティー
- こだわりグルメ
- ジュース・ドリンク
- お酒
- 絶品スイーツ
- ケーキ
- お菓子
- プリン
- フルーツギフト
- リラックスグッズ
- アロマグッズ
- コスメ
- デパコス
- インテリア
- キッチン・食器
- グラス
- 家電
- ファッション
- アクセサリー
- バッグ・ファッション小物
- ブランド腕時計(メンズ)
- ブランド腕時計(レディース)
- ベビーグッズ
- キッズ・マタニティ
- カタログギフト
- 体験ギフト
- 旅行・チケット
- ダレスグギフト
- ペット・ペットグッズ
- 面白い
- 大人向けのプレゼント
- 贅沢なプレゼント
- その他ギフト
- プレゼント交換
- 絆ギフト券プロジェクト
- リモート接待・5000円以下
- リモート接待・8000円以下
- リモート接待・10000円以下
- リモート接待・10000円以上
- おまとめ注文・法人のお客様
伊勢崎満 備前徳利①
-
商品説明・詳細
-
送料・お届け
商品情報
残り 1 点 8,360円
(6 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 02月08日〜指定可 (明日12:00のご注文まで)
-
ラッピング
対応決済方法
- クレジットカード
-

- コンビニ前払い決済
-

- 代金引換
- 商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥299,000 まで対応可能)
- ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
-
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行 - Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)
-





















![POP UP PARADE ガッツ [狂戦士の甲冑] L size](https://static.mercdn.net/item/detail/orig/photos/m37911047717_1.jpg)







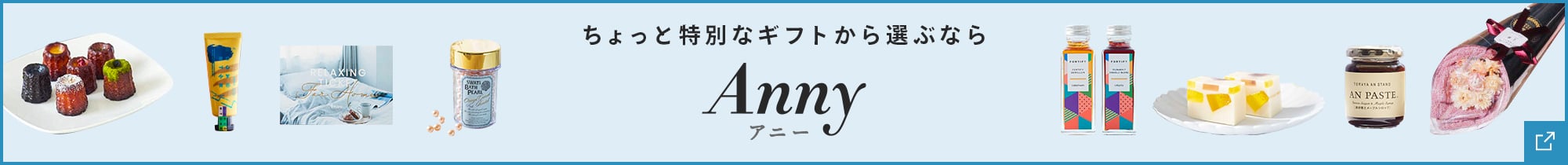




伊勢崎満 備前徳利①
サイズ H12㌢w(胴)5.5㌢
共箱、共布(印あり)陶歴付
得意のらっきょう型の徳利です。首下から胴にかけて黄胡麻がかかり、腰の明るく抜けている部分も見所となっている作品です。造形も優しい姿で何度も使って見たくなります。
陶歴
1934年 岡山県備前市伊部生まれ。伊勢崎陽山の長男、弟は人間国宝の淳。
1959年 日本伝統工芸展初入選。
1962年 日本工芸会正会員。鎌倉期古窯の復元に成功。
1974年 金重陶陽賞。
1984年 岡山日日新聞文化賞。
1990年 岡山県文化奨励賞。
1994年 山陽新聞文化功労賞。
1998年 岡山県重要無形文化財保侍者認定。
2000年 岡山日日新聞芸術文化功労賞を受賞する
2003年 ギャラリー陶魚庵を新築する
2005年 日本伝統工芸展で初入選する
2006年 作品が東広島美術館の買上げとなる
2007年 小形登窯と穴窯を築窯する
2011年 8月28日逝去
岡山県出身 岡山大学特設美術科彫刻専攻卒 岡山県指定重要無形文化財
細工物の名工であった伊勢崎陽山の長男として生まれる。
幼少期より弟、淳と共に陶技を父に学び、大学卒業後から本格的な作陶を開始。
1959年に日本伝統工芸展初入選、以降入選を重ね62年に日本工芸会会員に就任、
同年に弟の惇と共に平安時代の穴窯の再現、焼成に成功、84年にはさらに登り窯へと全面改装を実施。
古備前への深い造詣と父や大学に学んだ細工、彫刻の技法を巧く取り入れた斬新なデザインで
備前焼に新風を起こし、弟伊勢崎淳とともに現代備前焼の基盤を確立した。
陶印は「満」「陽山」 箆彫「イ」など